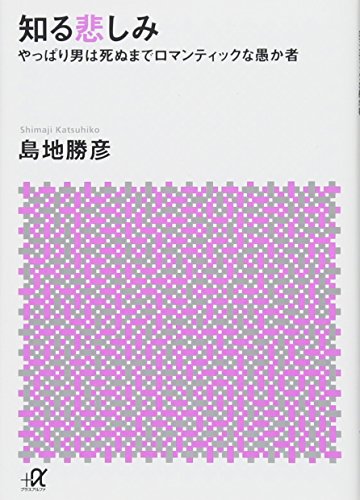先日数年振りに再会した大学の同級生にこの本を勧められた。彼は昨年度会社を辞め、現在言語聴覚士を目指し学校に通っているらしい。この本は彼のキャリアチェンジの一つのきっかけだったとのこと。たまたま自分が吃音持ちで過去に言語療法士*1の先生にお世話になったことがあると話し、なんという偶然かと2人して驚いた。
どのように吃音と向き合ってきたか
これまでも自分の幼少期の吃音やそれがましになった理由を漠然と考え、家庭環境や自分の精神成熟度に説明を求めようとし、結局よく分からないままだった。というよりも、よく分からないまま大人になることができた幸運な人間だった、と言うべきなのかもしれない。自分の症状はこの本に登場する人よりもおそらく軽い。軽い、というのは就業の機会等において不利益を受けることはなかった、という意味である。吃音はましになったにせよ、もちろん身体には"どもる"感覚がしぶとく生き残っている。発話に困難を覚える生々しい感触は消えない。この身体的特徴は、個々人の置かれた状況によって、苦痛や異常にもなれば、取るに足らない無数の人間の仕草の一つにもなり得る。ある時は個性かもしれない。この本は、丹念な取材を踏まえ、何人かの主人公のレンズを通し、吃音との向き合い方を考えさせてくれる作品である。自分はどうだったのだろうか?どのように吃音と向き合ってきたのだろうか?思い返せば、吃音を治すつまり問題を解決するという発想ではなく、どれだけ少ないコストで吃音と共存できるか、を常日頃から考えてきた気がする。
小学校から中学校時代に、言語療法士の先生に定期的に診断を受けていた。確か隔週ぐらいの頻度で車で30分ほどの病院に母親と通っていた。診断、といっても大したことをするわけではない。毎回国語の教科書を持っていき、本をゆっくりと読む練習をする。そのときメトロノームを使って、アンダンテ(歩くようなスピード)で本を読む。本を読みながら少しテンポが早くなったりすると、アンダンテ、アンダンテと何度も言われたことを覚えている。本読みが終わると、後は絵を描いたり、手品を練習したり、遊んで過ごした。おそらく脳の機能を検知する等、何らかの意図や目的のある作業だったとはずだが、自分にとっては楽しいだけの時間だった。
当時、自分の吃音について親や先生に悩みを相談した記憶はない。瞬間的には嫌な思いをしたこともあるが、思い悩むというよりも、吃音の原因、傾向や対応策を、ある種客観的に掴もうとしていた。
過去にたった一度だけ、同級生に自分の吃音について聞かれたことがある。小学校低学年の時の帰り道。「なんで普通にしゃべられへんのん」と。その時は、病院に行ったり話す練習もしてるがうまくいかない、と答えた気がする。小学生なんて好奇心の塊だし、疑問に思うのも当然。この時自分は、同級生の問いかけに対して、悲しいとか辛いよりも、本当になんで自分は喋れないんだろう、なんでなんで、と家に帰るまでなぜを考えていた。
例えば、当時は毎日発音しにくい音が変わっていたため、それらの記録を付けたりなんかもした(ある日は"サ行"が言いにくい、別の日は濁音が言いにくい、など)。愚直にどもった回数をノートの端っこに正の数にして書いたこともある。また、会話の最初の音が発音しにくい時は、小さい"ン"を助走するかのように発声しながら話す、手や足を小さく振りかぶりながら話す、同じ意味で発音しやすい言葉に言い換える、そのためにボキャブラリーを増やす、等色んな方法を試した。
むしろスラスラ話せることがおかしいのではないか
試行錯誤の中で、言葉をメロディーに乗せて歌うように発音するとどもらない、ということも分かった。個人的にはこれを「ミュージカル仮説」と呼んでいて、本来人間の音声的なコミュニケーションは音程が伴うものだったが、社会が複雑になるにつれ効率的に情報を伝達する必要性が生まれたため、フラットな発話方法を取得したのではないか、と考えている。この仮説に従うと、ミュージカル風に音程をつけて発話するのは単に人間生来の話し方をしているだけであり、おかしいのは平坦な抑揚での発話を強制する社会の方じゃないかと、窮屈な発話を強いられているのだから自分はどもって当然だと、本気で思った時期もあった。誰か賢い人、検証してほしい。
結局、どんな局面でも汎用的な対応策は見つからなかった。しかしこれによって、吃音に対処するハウツーのようなものはなく、精神的に落ち着くことが大事なのではないか、という気づきを得た。そしてこの精神的な安定こそが、年齢を重ねるにつれ自分の吃音がましになった理由ではないか、と思えるようになった。他人と接する怖さや緊張が、年とともに緩和されていくという単純な考えである。単純だが、幼少期の吃音経験者の多くが成人になるにつれ症状が改善されていく事実に鑑みると、割と納得感のある説明だとも思う。自分も例外ではないと思う。
吃音で良かったこともある
この本以外にも吃音をもつ人物が登場する作品がいくつかあり、中でも『英国王のスピーチ』や重松清の小説等は有名だと思う。個人的には吃音持ちの主人公(満島真之介)が登場する『風俗行ったら人生変わった』という映画が印象的だった。
詳細は忘れたが、この映画の中で佐々木希が主人公に「吃音の人は嘘をつかない。本心をしゃべってくれる」みたいなことを言っていて、流暢に話せないというビハインドをこうもポジティブに捉えることができるのか、と感心したのを覚えている。
また、元プレイボーイ編集長の島地勝彦さんも吃音持ちだったという。同じ身体的特徴を有する、という意味ではある意味得難い経験をさせてもらっているのかもしれない。
*1:当時の言語聴覚士の名称。